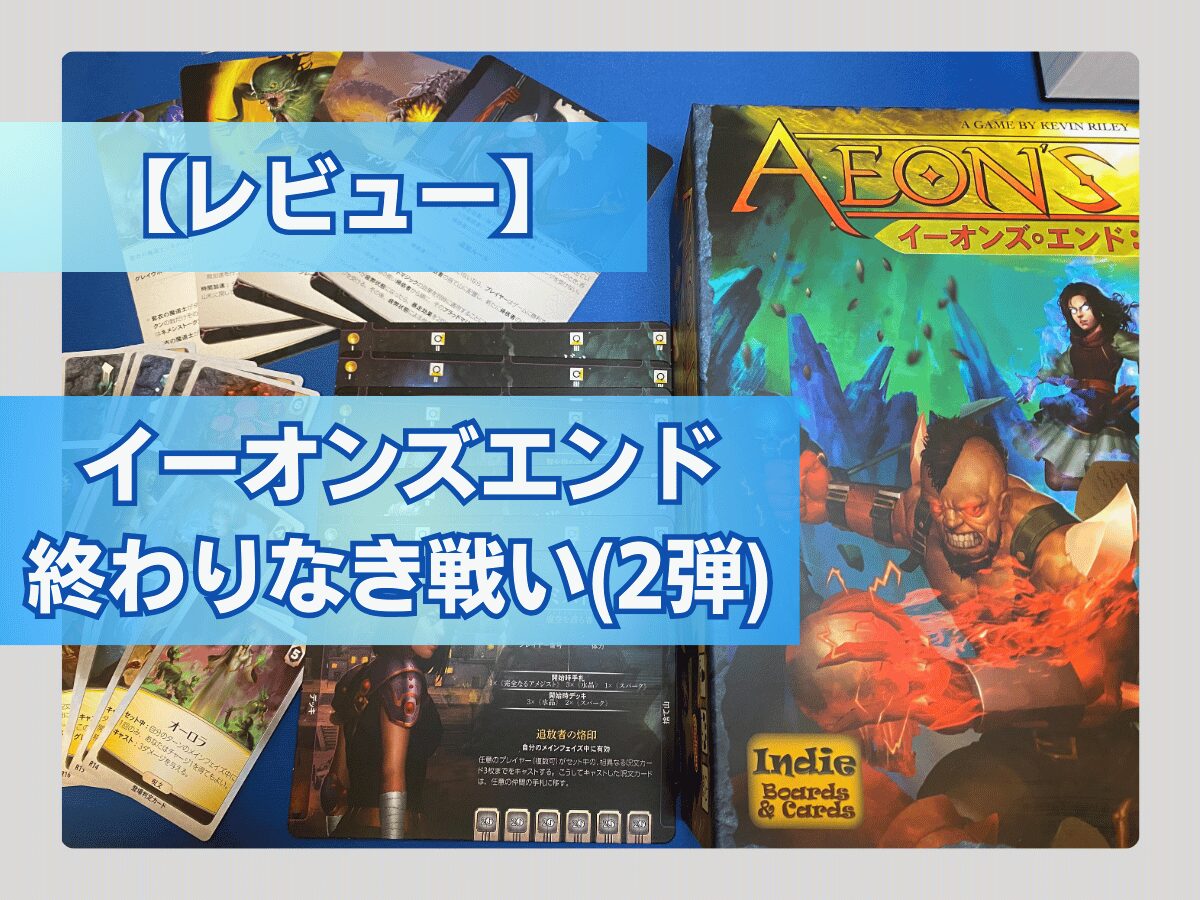第2弾の基本セットである『イーオンズエンド:終わりなき戦い』のプレイが終了しました!
第1弾よりネメシスの難易度が高くなっており、それに伴ってキャラクター能力とカード効果の強さとクセが高まっている印象でした!
純粋に難易度が高いので苦戦必至ではありますが、プレイヤー側も強化されているので、上手にデッキ構築を行いプレイヤー同士の連携が噛み合った時の破壊力は爆発的。前作以上に知略要素と爽快感の増したネメシスとの死闘を楽しむことができました!
グレイヴホールドは「かつて在りし世界」の最後の堡塁として踏みとどまっていた。
「名無きもの」としてのみ知られる怪物らによる、別世界からの侵攻が苛烈を極めているさなか、虚空から奇妙な生存者グループが出現した。
彼らがグレイヴホールドにもたらすものは、救済か、それとも破滅なのか。
この記事では、”実際のプレイデータ“、評価”、そして”プレイの感想”を共有したいと思います!

ぼどわん(当サイトの運営者)
- 一般企業勤めの20代後半
- 協力系ボードゲーム、謎解き大好き!
- 負けず嫌いなので対戦系はほどほどに…(笑)
- 100種類以上のアナログゲームを保有、順次紹介!
イーオンズエンドの紹介記事、遊び方に関してはコチラから!
-
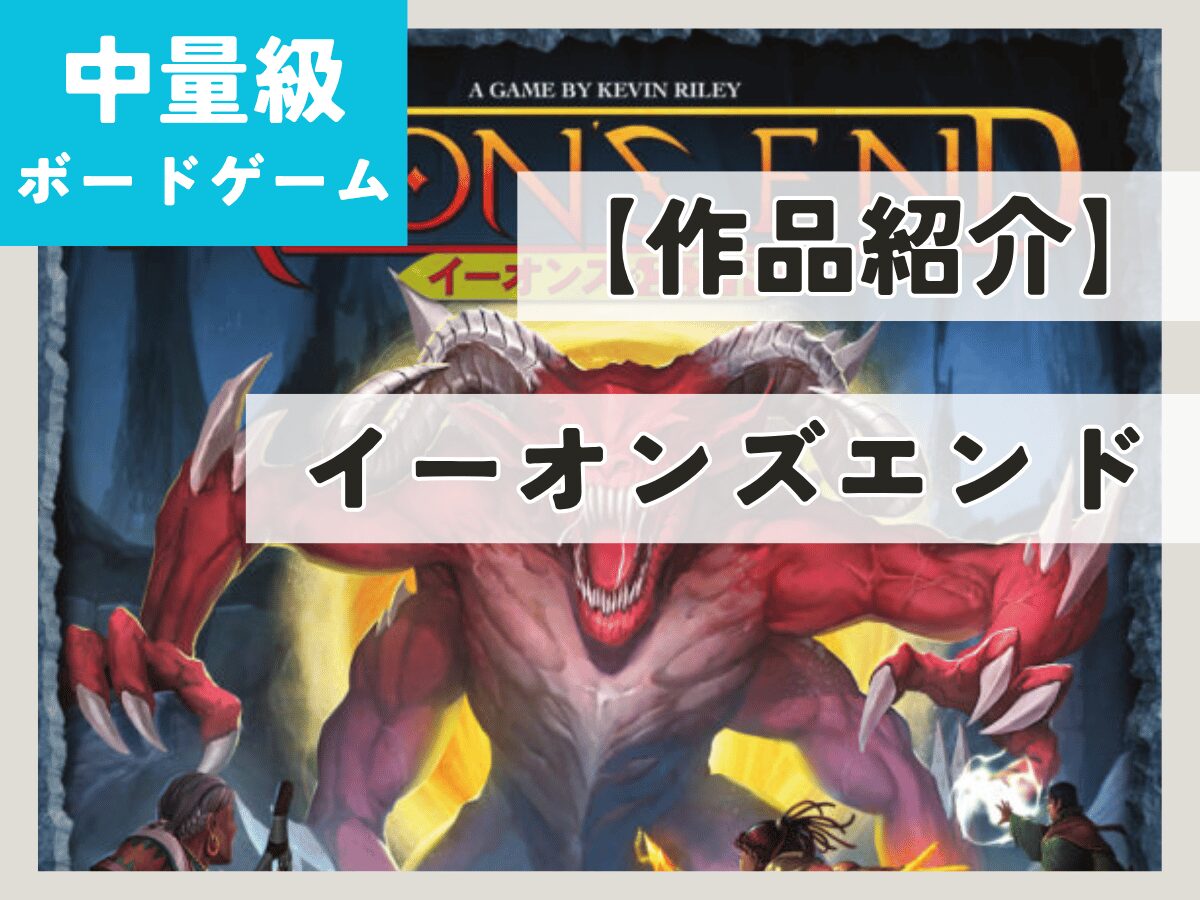
-
【ボドゲ紹介】「イーオンズエンド」シリーズ徹底解説
今回紹介するゲームは【イーオンズエンド】です!イーオンズエンドはデッキ構築型の協力ゲームで、カード選択、獲得、プレイの仕方で全てが分岐する戦略型のボードゲームです! プレイヤーは魔術師となり、人類最後 ...
-
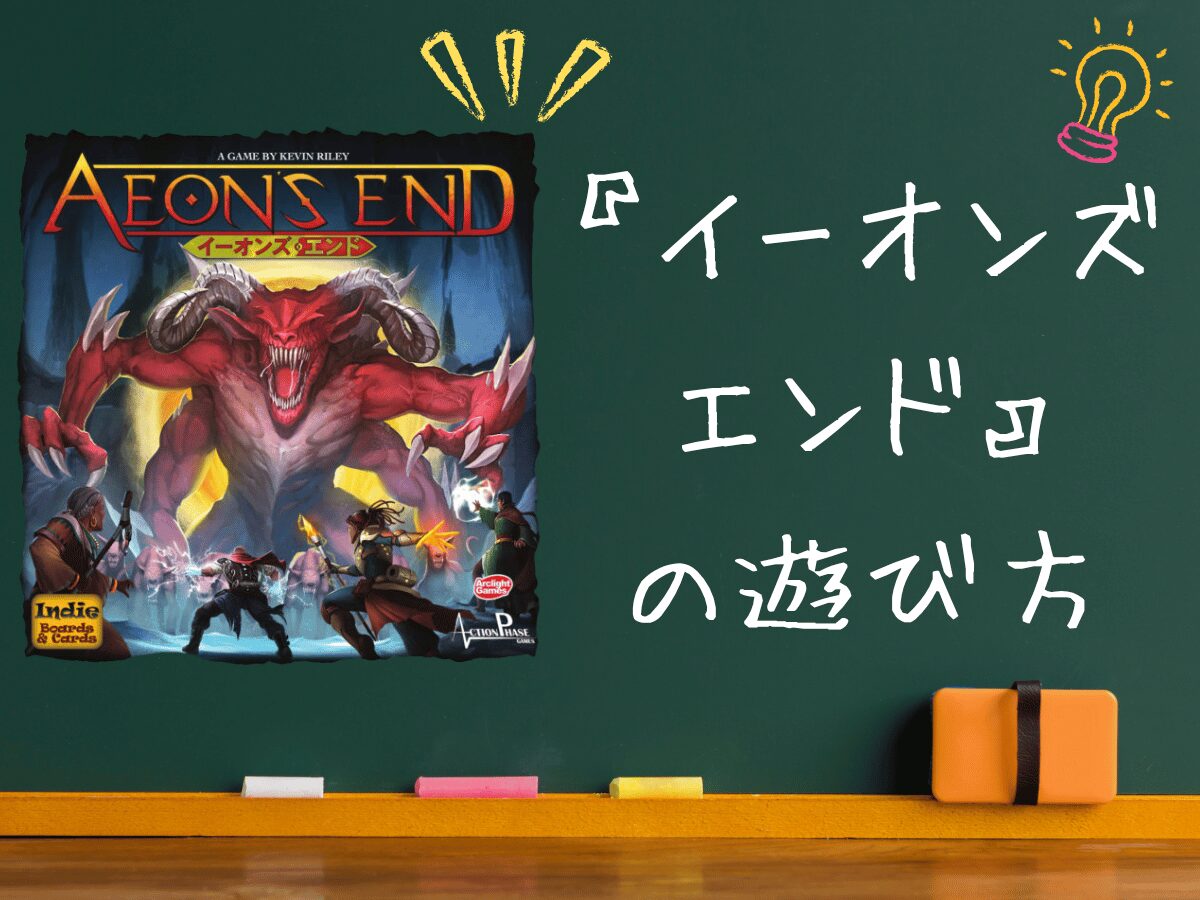
-
【遊び方】イーオンズエンドのプレイ方法解説(画像/動画付き)
ここでは、ボードゲーム『イーオンズエンド』の遊び方を動画、画像付きで紹介します。 Contents1 ゲーム概要2 プレイ解説動画3 プレイ解説画像3.1 ①準備1(選択)3.2 ②準備2(盤面の準備 ...
Contents
実際のプレイデータと評価
まずは、実際のプレイデータと評価を記載していきますね!
通常・熟練者モードの計2周で全19回プレイ

二人プレイでイーオンズエンドのプレイ終了までには以下の通りになりました!
プレイデータ
- プレイ人数 : 2人
- プレイ時間 : 12時間35分(1プレイ39分程度)
- プレイ回数 : 19回
- プレイ期間 : 11日間(7月10日~7月20日)
イーオンズエンド作品に共通しますが、使用するキャラクターとカードセットの組み合わせでかなり膨大な通り数があるので、リピート性は非常に高く、飽きずにプレイし続けられるのが魅力的ですね。
また、本ボドゲには“初心者”、“通常”、“熟練者”、“自殺志願者”の4種の難易度がありますが、私は通常と熟練者でプレイしており、まだ自殺志願者モードでのクリアという遊ぶ余地を残してます。

自殺志願者級はあまりに厳しくて、ちょっと気が引ける(笑)
19回プレイしてもなお、キャラクターの特性とそれを活かしたカードセットの探索ができていない部分も多く、ここら辺ももう少しやりこんでみたいポイントでした!
運要素少なめの知略ゲー好きにはオススメ!
実際にプレイしてみて、『イーオンズエンド:終わりなき戦い(第2弾)』の評価はコチラの通りになります!
プレイ評価
| 盛り上がり | :4 | |
| 難易度 | :4 | |
| 知略 | :4 | |
| 運要素 | :2 | |
| コスパ(ボリューム/時間) | :4 | |
| おすすめ度 | :3 |
個人的に数あるボドゲの中でも高評価なシリーズです。
また、5段階だと数値には反映できないですが、前作より難易度と知略、運要素が0.5ポイントずつは上がってる印象を受けました。第1弾と第2弾でストーリー上の繋がりはあるものの非常に薄く、いずれも基本セット(独立拡張セット)なので、難易度高い方がお好きであれば第2弾から購入しても問題ないかと思います。
現在(2025/7)、第5弾まで登場していますが、拡張セットがあるのは第1弾〜第3弾までで、第2弾の拡張性が高いのも利点ですね。

第3弾は少し値が張るレガシー型作品で、拡張は1種のみだよ!
プレイの感想(ネタバレなし)
さて、本ゲームのプレイ感想に移ります。
デッキ構築とキャラクター特性のマッチを追求
ネタバレ抜きのレビューは基本的に第一弾の基本セットをプレイした感想と同様です。
ただ、本作は第一弾よりも難易度が上がってることで“デッキ構築”と“キャラクター特性”の相乗効果が必要な印象でした!
イーオンズエンド作品のデッキ構築はユニークで
① カードセット選択:キャラクター特性や敵の能力に応じた使用カード選び
② リアルタイムデッキ構築:毎ターン、エーテルを消費することでカードを獲得し初期デッキを拡張しながらバトル
③ ノーシャッフルシステム:山札が尽きた時、捨札をそのままひっくり返し、そのままの順番だ山札として使用
の3つから成り立ってます。
カードセット選択はカードゲームの醍醐味の1つですが、イーオンズエンドではさらに捨て札がそのままの順番で未来の山札になるので、この点を考慮しながらカード獲得、使用を行い、キャラ固有の初期デッキを強化しながら戦いを進めます。
この戦術性が非常に楽しく、バトル終盤においてはキャラ能力とデッキ構築が噛み合った時の高火力による逆転劇は爽快でしたね!

ネメシスHPの半分以上を占める44点ダメージをぶつけることができたよ!
ゲーム難化による役割分担の重要性の向上

イーオンズエンドは協力型カードゲームなので、第一弾の基本セットでも役割分担を行う必要性はあったんですが、第二弾は難化しているため、その重要性が更に増しています。
第一弾の基本セットでは正直、オフェンシブなキャラクターのみで火力こそ正義的な速攻型のプレイでもクリアできたりもしました。
一方、第二弾では厄介な状況に直面することが増え、プレイヤーおよびグレイヴホールドのHPがゴリゴリ削られるので、サポートとアタッカーを併用して耐久力を高め、キャラクターだけでなくデッキ構築も協力しながら進める必要性が増し、より協力ゲーム要素が高まっていましたね。
攻めっ気が強いペアの場合でも、第二弾ではサポート兼アタッカーなキャラクターや両方の要素を兼ね備えるカードも出現しているので、そこは様々なペアの需要を満たせる作りになってますね。
プレイの感想(ネタバレあり)
次はネタバレありで、プレイ感想を述べていきます。
なお、第2弾シリーズの各カードの全評価については下記記事を参考にしてください。
-
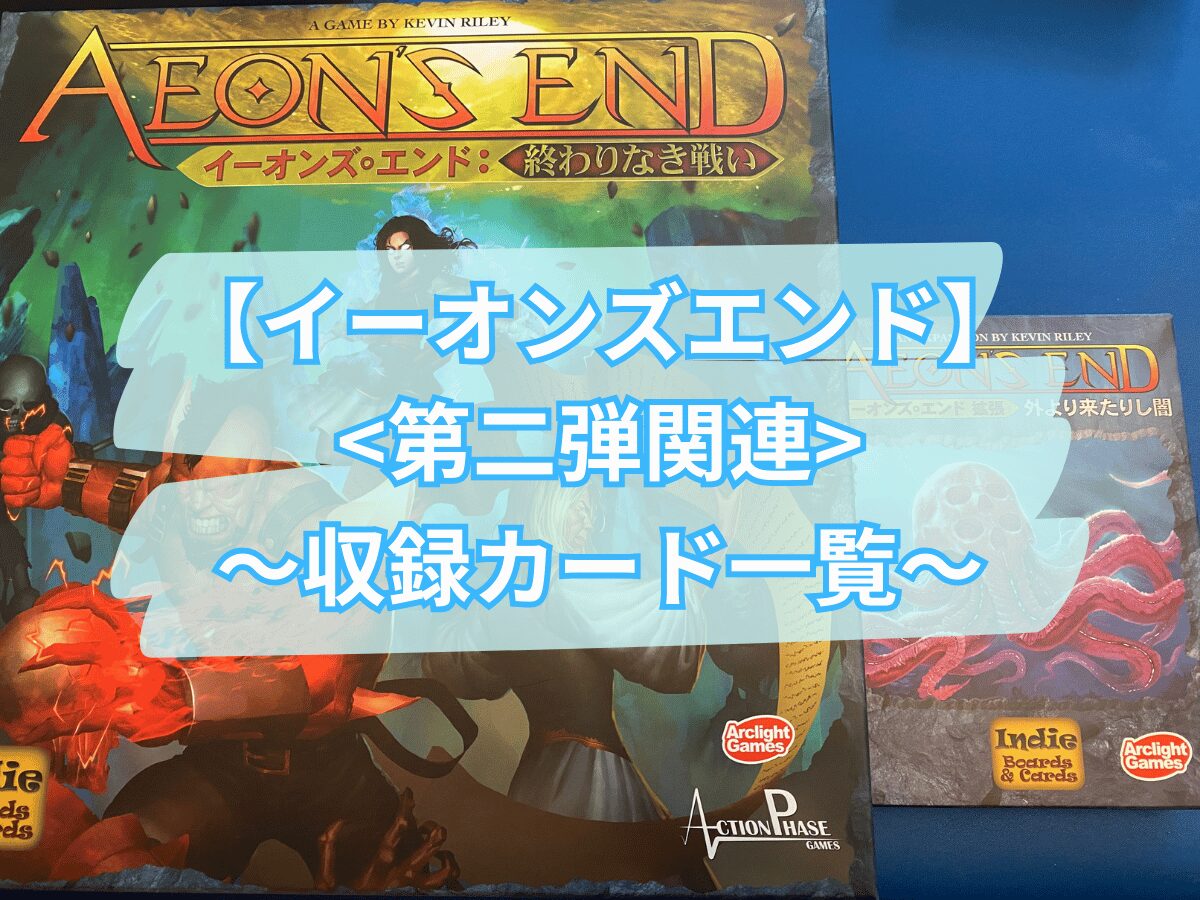
-
【攻略】イーオンズエンド<第二弾>収録カード一覧
本記事ではイーオンズエンド第二弾関連の収録カード一覧と個人的な評価をまとめていきます。 もし、効果内容が不明瞭な場合や、攻略に困る場合はコチラを参考にしてくださいね。 さっそく、第二弾関連の”カード一 ...
キャラクター紹介
本作品に収録されているキャラクターは8種。
中でも、ネメシス攻略の難易度が上がってるため、サポートキャラによる「プレイヤーorグレイヴホールドの回復」は重宝します。この回復を担えるサポートキャラが「マザヘドロン」と「ゲクス」、「ウルギモール」の3体です。回復効果を持つカードも存在しますが、これらのサポートキャラを使用することでより盤石に戦闘を進められる他、そもそもカードセット選択で選ぶ回復系カードを絞ることができるので、アタッカーと組み合わせた2キャラを選択するのが非常に強力なコンビでした。
サポートキャラ



「マザヘドロン」はグレイヴホールド体力4回復+コスト4以下の宝石カードを入手できます。「ゲクス」は味方の体力2回復と効果は小さいものの、カード1枚追加ドロー+自分の捨て山2枚破壊のデッキ圧縮が強力です。一方で「ウルギモール」は自分の体力6回復か疲弊状態なら味方の体力5回復という回復の鬼ですが、彼の固有カードである「石炭片」が体力を削って大量のエーテルを獲得する効果なのでバランスが難しいです。
個人的には「ゲクス」は好きですが、案外体力回復が追い付かないので、「マザヘドロン」を使用してカードセットに体力回復を組み込むパターンを良く使ってましたね。
アタッカーキャラ



次にアタッカーキャラとしては「キリウス」「デズモディア」「ガル」の3種がいます。サポートキャラ+アタッカーキャラの組み合わせがやはり安定しますので、ここら辺もよく使用しますね。
「キリウス」は本作品で追加されたトロフィートークンを使用したユニークな能力を持っており、固有カード「消殺」で敵を倒すたびに付与されるトロフィートークンに応じたダメージを放つことができます。とはいえ、低ダメージの「消殺」で都合よくミニオンを倒すのも難しければ、ランダムで選ばれるネメシスデッキの中にどれだけミニオンが混入するかも不明なので少し使いづらい印象でした。チャージ効果のある呪文との組み合わせで永遠にダメージを放てるデッキ構築は面白そうですね。
「デズモディア」も本作品で追加された特殊な破孔を使用したユニークな能力を有し、破孔Ⅰ~Ⅱの進化でダメージ+2が恒久的に付与されます。ただチャージ6必要なので案外重く、使い勝手が悪い印象です。
「ガル」は本作品のOverPowerキャラですね。能力はセットされた呪文を破棄して「2+破棄枚数×4」のダメージを振り分けることができます。ガルの固有カードが破孔の強化なので破孔の開放が次々に進むのに加えて、スパークのような低ダメージ呪文が能力により中級呪文に生まれ変わります。そして特筆すべきは“ダメージの振り分け”です。「ミニオンHP2に対して6ダメージ呪文を使用しなければならない場合」や「呪文のダメージによらず、実質5回攻撃しないと倒せない場合」に度々遭遇しますが、ガルの能力では振り分けることができるので無駄なく処理できます。序盤、中盤、終盤のどのフェーズにおいても強さを高い水準で発揮できるキャラクターでしたね。
特殊キャラ


回復効果を有しないサポートキャラクターの位置づけが「ミスト」、「ヤン・マグダ」の2種存在します。

ミストは前作に引き続き登場したキャラクターだけど、性能が変わってるね。
「ミスト」はセット呪文をキャストして仲間の手札に移すというもの。以前は味方4枚ドローの能力でしたが、作品難易度の上昇に伴い、若干縛りができて強化されています。過去作品から生き残って成長したということですかね。前作からの地味な話のつながりはあるようです。能力の感想としては…純粋に味方の呪文をキャストして再度手札に戻すのも良いですが、破孔を最大まで開放してもセットできるのは4つまでなので、呪文であふれかえる可能性があります。自身の呪文をキャストして味方に送るのもいいですが、そのためには宝石の獲得、強力な呪文の獲得、破孔の強化とやることが多く、実質上手に活用できるのは終盤になります。案外縛りが多く使い勝手が悪い能力かなと思いました。
そして最後、「ヤン・マグダ」は破孔最大強化でサプライカードを無条件で1枚入手できます。本作の特徴として破孔最大…とかサプライが空…とか条件付きの強化があるのが一癖あって面白いですね。能力的には「ヤン・マグダ」の破孔解放は結構重いのと、チャージ5(エーテル10)を使用してまで味方に上げたいカードが特に思い浮かばず、有効な使い方が最後まで思いつきませんでした。個人的な最弱キャラでしたね。2人プレイ以外なら使える状況があるのかもしれません。
カードセット
次にカードセットについてです。
本作品に収録されているカードの種類は宝石カードが7種、遺物カードが6種、呪文カードが14種の全27種類です。この中から宝石カード3種、遺物カード2種、呪文カード5種を選択し、戦闘を行います。なので、カード選択だけでも組み合わせが膨大にあります。さらにはキャラクター特性を考慮して最適解を選んだりするので、やりこみ要素は多いですね。
※なお、登場判定カードと呼ばれるカードセット選択をランダムにできる仕組みもあります。
あまりにも数が多いので、印象的なカードのみレビューします。
宝石カード

宝石カードは序盤においてデッキ構築を加速させるうえで非常に重要です。初期手札には大抵「水晶」が3~4枚あるので、コスト3~4の宝石は序盤でも入手しやすいです。
そういった観点から「火山岩滓」が強力でした。4コストでエーテル2と序盤はややコスパが悪いですが、ネメシス階層が2以上になった時にはエーテル3になります。中盤以降は4コストでエーテル3となるので安定して強力でした。
また、「異常鋳塊」は5コストでエーテル2、捨て山にネメシスのターン順カードがあればエーテル4になるカードも頻繁に使用していました。ややランダム要素はありますが、5コストでエーテル4になるのは強力。ただ半分の確立で腐るので、そこは山札を調整して少しでも確立を上げる必要があります。コスト6まで行くとカード獲得難易度が高くなりますが、コスト5までであれば比較的容易に獲得できますからね。
遺物カード

遺物カードはもうほぼ固定でしたので、「魔物捕獲器」と「原始的呪物」が安定して強力でしたね。
「魔物捕獲器」はデッキ圧縮カード。手札あるいは捨て山のカードを破壊+ターン順カードを公開してネメシスならターン順カード山札の底に移動可能。デッキ構築においては強力なカードを獲得するほど、序盤の弱カードが邪魔になるので、圧縮カードは必須級。これだけでも強いのに、ネメシスターンの遅延効果もあり、早急にミニオンやパワーカードの処理をする必要がある場合に何度も救われてました。
「原始的呪物」はプレイヤーの破孔強化or破壊して体力3回復です。序盤中盤にかけての破孔強化と、終盤の臨時回復で全く腐ることがありません。特に遺物は序盤に入手するほどお得なので、原始的呪物を序盤に獲得するだけで破孔3つ目までは余裕で解放できます。
呪文カード

呪文カードは「失われし者の召喚」と「オーロラ」が非常に強力でした。
「失われし者の召喚」はコスト6とやや獲得難度は高めですが、純粋に6コス5ダメージはイカれた性能をしています。そして、特筆すべきは任意で破壊することでグレイヴホールド体力4回復可能なこと。ダメージ兼回復保険になるこの呪文性能は本作一番のOverPoweredカードでした。
次に「オーロラ」です。こちらは5コストで3ダメージ+セット中1チャージという能力。5コストで3ダメージはやや物足りないですが及第点。ただし、チャージ効果があるので戦闘が非常に安定します。サポートキャラでオーロラを複数積めば基本的にはプレイヤーあるいはグレイヴホールドのどちらかが完全に安泰になります。個人的にはキリウスでトロフィー貯めてオーロラガン積み構成を試してみたかったですね。
ネメシス

最後にネメシスの紹介です。
本作ではネメシスは4種収録されています。ネメシスの難易度は10段階で、③⑤⑦⑦の難易度が収録されています。前作のネメシス難易度は②④⑤⑤でしたので、圧倒的に難化していることが分かると思います。

本作で一番印象的だった(苦戦した)ネメシスは意外にも難易度⑤の『虚ろなる冠』です。
ぶっちゃけね…。
“熟練者モード”以上の難易度でプレイした時の“難化ルール”がおかしい…!!
恐らくですが、記載の難易度は通常モードでの攻略難易度を表していて、難化ルールは全く反映されていません。

虚ろなる冠の特徴はミニオンのほかに、帰依者と呼ばれる敵が2体ずつ出現すること。勝利条件は全9体存在する帰依者を全て撃破することです。帰依者自体のHPは11固定なので、99ダメージ必要になります。ミニオン処理も並行して行うので、ほかのネメシスより必要ダメージは多いですね。
さらに暴走効果は体力の多い帰依者の効果を発動するというもの。通常モードならば純粋に帰依者の効果が強いほうを早めに削れば対処可能なので、確かに難易度⑤は妥当かなと思います。
が、“難化ルール”になると話が変わります。暴走効果により場にいる帰依者2体の効果がどちらも発動されます。これが本当に頭がおかしくて、「手札2枚捨てる」やら「プレイヤー2ダメージ」やら「グレイヴホールド3ダメージ」の効果がある中で暴走の度に複数の効果が適用されます。序盤で暴走効果を持つ階層1のミニオンが組み合わさったらもう凶悪で、なすすべなく負けます。

虚ろなる冠の難化モードは7回失敗したね笑
まとめ
本記事では紹介しなかったネメシス等も非常にユニークな能力を有しており、各戦闘が非常に楽しかったですね。熟練者モードのさらに上、自殺志願者モードをクリアしようとすればさらにプレイ回数が増えることになるので、低価格でありながらリピート性の高いボードゲームといえます。プレイヤー選択とカードセットの組み合わせも多く、好みの構成を模索するのも非常に楽しいポイントですね。単純な繰り返しボードゲームでありながらここまでリピート性が高いのは魅力的な作品でした。
加えて、1プレイが1時間以内で完了する中量級ボードゲームであることもGOOD。
「イーオンズ・エンド」シリーズ全作品をプレイしてみたくなるほどハマれるボードゲームだったので、カードゲーム好きは勿論、ボドゲ初心者さんにも十分おすすめできる作品でした!